ジョージ・オーウェルの『動物農園』、原題は『Animal Farm』
邦題では「動物農園」と「動物農場」の両方のタイトルがあるようですね。
ずっと気になっていたけれど、なかなか手を出せなかったこの本。
最近はミステリー小説を多く読んでいたので、少し違うジャンルの本を手に取ってみたくなり、今回ようやく読むことができました。
この小説は、1945年に発表された風刺的な寓話小説です。
物語は、動物たちが農場主の人間を追い出し、自分たちの理想を基にした社会を築こうとするところから始まります。
ですが、やがてリーダーとなった豚たちが権力を握り、当初掲げていた平等や自由の理念は次第に崩壊。
最終的には独裁的な体制が確立されてしまいます。
では、ここから私の感想を綴っていきたいと思います。
もくじ
書籍情報
原題:Animal Farm
著者:George Orwell
発表年:1945年
邦題:動物農園
著者:ジョージ・オーウェル
訳者:吉田健一
装画:ヒグチユウコ
出版社:中央公論新社
発売日:2022年9月20日
ページ数:155ページ
動物農園のあらすじ
ある農場で、動物たちは人間の支配に反発し、平等で自由な社会を目指して反乱を起こす。
当初は理想的な共同体を築こうとするが、やがて豚たちが権力を握り他の動物を支配する立場に転じていく。

特に、ナポレオンという豚がリーダーになると、追放したはずの人間と同じような独裁的な体制を強いていき・・・・。
この物語は、権力の腐敗や、革命後に理想がどう崩れていくのかを象徴している作品です。
主要動物のキャラクター

- ナポレオン(Napoleon) – 豚
- 農場を革命後に支配する独裁者。
権力を掌握するためスノーボールを追放し、他の動物たちを従わせる。
- 農場を革命後に支配する独裁者。
- スノーボール(Snowball) – 豚
- 革命後、農場をより良くしようとする理想主義的なリーダー。
スノーボールは賢く情熱的ですが、ナポレオンにより追放され失脚する。
- 革命後、農場をより良くしようとする理想主義的なリーダー。
- スクィーラー(Squealer) – 豚
- ナポレオンの側近。
嘘を広め情報を操作する、権力者のプロパガンダを象徴する存在。
- ナポレオンの側近。
- ボクサー(Boxer) – 馬
- 労働者階級の象徴。
彼のモットー「自分がもっと働けばいい」(I will work harder)
「ナポレオンが間違うはずがない」(Napoleon is always right)
ボクサーが支配者に従順であることを表している。
- 労働者階級の象徴。
- クローヴァー(Clover) – 馬
- ボクサーの仲間。
クローヴァーも支配者に疑念を抱くが、行動に移すことはしない。
- ボクサーの仲間。
- ベンジャミン(Benjamin) – ロバ
- 物事が良くなることはないと信じている気難しいロバ。
最も長生きで、最も物事を理解しているが、何も行動を起こさないキャラクター。
- 物事が良くなることはないと信じている気難しいロバ。
- モーゼス(Moses) – カラス
- 権力者の意向に従いながら動物たちを操る存在。
モーゼスが語る「砂糖菓子の山」(Sugarcandy Mountain)は、死後の理想郷を象徴している。動物たちに幻想を与えながら現実の苦しみから目を背けさせる役割。
- 権力者の意向に従いながら動物たちを操る存在。
- モリー(Mollie) – 馬
- リボンや角砂糖を好む馬。
モリーは自己中心的で、理想よりも個人の快適さを優先するキャラクター。
- リボンや角砂糖を好む馬。
- ミュリエル(Muriel) – ヤギ
- 読み書きができる特異な存在。
他の動物たちのためにルールを読み上げるが、変わりゆく現実の中、次第にその重要性が薄れていく。
- 読み書きができる特異な存在。
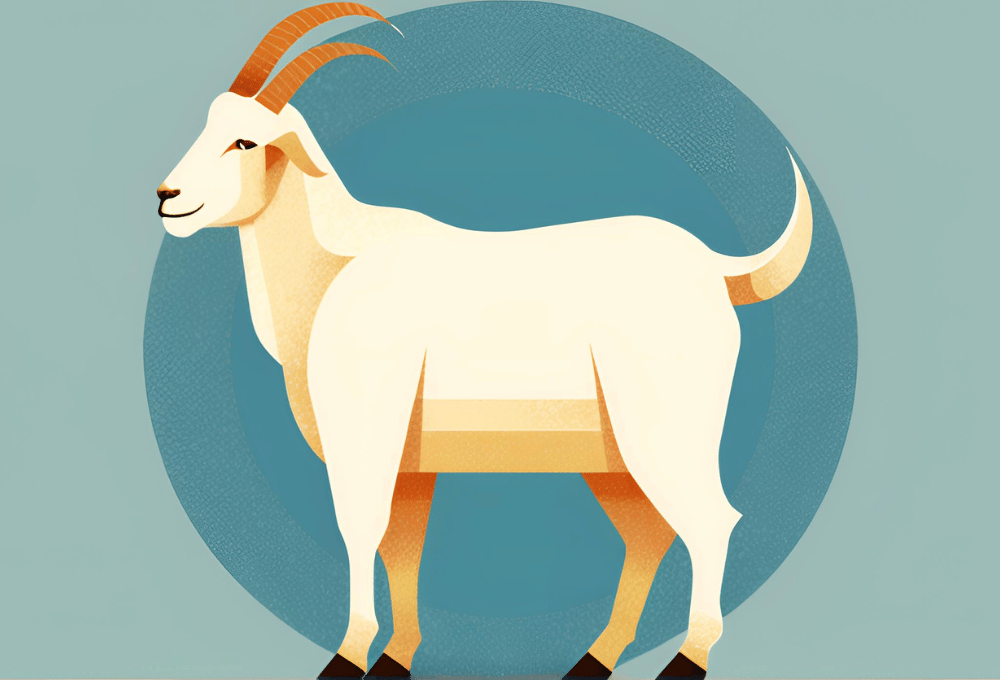
その他のキャラクター
- ミニマス(Minimus) – 豚
ナポレオンを賛美する詩や歌を作る、プロパガンダ要員の一人。 - 犬たち(The Dogs)
(ブルーベル、ジェッシー、ピンチャー、9匹の子犬)ナポレオンの私兵として忠実に仕え、反対者を脅し追い払う存在。 - 羊たち(The Sheep)
支配者の指示に盲目的に従う群衆。
「4本足は良い、2本足は悪い」というスローガンを無思考に繰り返すプロパガンダの象徴。

「七誡」という鉄の掟
人間を追い出したあと、「七誡」という鉄の掟ができました。
「七誡」は「しちかい」と読みます。「誡」は「戒」とも書くことができ、意味としては「戒め」や「教え」というニュアンスがあります。
「七誡」英語対応と意味
「七誡」は英語で「The Seven Commandments」と訳されています。「commandment」は「命令」や「戒律」という意味で、この戒めは、動物たちが人間の支配から解放され、動物農場を平等な社会にするために立てたルールです。
【七誡の内容とその英語訳】
すべて二本足で歩く者は敵である。
(Whatever goes upon two legs is an enemy.)
すべて四本足で歩く者、または翼を持つ者は友である。
(Whatever goes upon four legs, or has wings, is a friend.)
どの動物も衣服を着てはならない。
(No animal shall wear clothes.)
どの動物もベッドで寝てはならない。
(No animal shall sleep in a bed.)
どの動物もアルコールを飲んではならない。
(No animal shall drink alcohol.)
どの動物も他の動物を殺してはならない。
(No animal shall kill any other animal.)
すべての動物は平等である。
(All animals are equal.)
これらの戒めは、物語の中で動物たちの平等な社会を守るための基盤として設定されますが、ストーリーが進むにつれて次第に改変され、動物たちの理想が崩れていく象徴でもあります。
感想
作品自体は長くないので、2〜3回読み返しました。というのも、登場する動物たちが多く、それぞれの性格や物語上の役割を一度では把握しきれなかったからです。
繰り返し読む中で、特に気になったキャラクターがボクサーという馬。
ボクサーの生涯について考えると、とても複雑な感情が湧いてきます。ボクサーの無欲な労働観や自己犠牲の精神は、最初は崇高に見えます。
ボクサーは常に『もっと働けばいい』『ナポレオンは間違っていない』と信じ続け、自分がすべてを解決できると考え、誰にも責任を押し付けません。
その姿勢は、ある意味で尊敬に値しますが、同時に強い悲しみも感じました。

疑問を持つことも、反抗することもしないボクサーの忠誠心が、結局のところ利用され、最後には悲劇的な結末を迎えるという点が特に心を揺さぶります。
ボクサーは幸せだったのか?
もっと自由に自分の意思を持って生きられたかもしれないのに、それを自分から放棄してしまったのではないかと思わずにはいられません。
ボクサーの生き方は、時に疑問を持つことや自己主張をすることの重要性を思い出させてくれ、ただ従うだけではなく、自分自身の価値観で生きることがいかに大切かを、改めて考えるきっかけとなりました。
ジョージ・オーウェルはこんな人
ジョージ・オーウェルは、イギリスの作家、ジャーナリスト、エッセイストです。
本名はエリック・アーサー・ブレア/ Eric Arthur Blair
生まれ年:1903年6月25日
出身地:インドのビハール州モティハリ
父親がインドでイギリス統治部門の役人として働いていたため、1903年にインドのモティハリで生まれました。幼少期に母親とともにイギリスへ戻り、おもにイギリス南部のサセックスで育ちました。

【卒業後の経歴】
奨学金を得てイギリスのイートン・カレッジを卒業したオーウェルは、大学には進学せず、ビルマ(現ミャンマー)のインド帝国警察に勤務しました。ビルマでの植民地支配に対する不信感が芽生え、その経験は後の作家活動に大きな影響を与えました。
【作家を目指す】
1927年に警察を退職し、作家を目指してロンドンとパリで生活を始めました。この期間に貧困や労働者階級の生活を体験しました。
【オーウェルの晩年】
1940年代後半、オーウェルは健康を害し、結核を患いました。それでも執筆活動を続け、『1984年』を発表しました。1949年に再婚しましたが、1950年1月21日、結核の悪化により46歳で亡くなりました。晩年は病気と闘いながらも、彼の作品は次第にその影響力を広げていきました。
主な作品
ジョージ・オーウェルの作品は、社会主義や政治的権力、言語の使用とその影響をテーマにしたものが多く、特に以下の作品が有名です。
- 『パリ・ロンドン放浪記(Down and Out in Paris and London)』(1933年)
- 『ビルマの日々(Burmese Days)』(1934年)
- 『カタロニア讃歌(Homage to Catalonia)』(1938年)
- 『動物農園(Animal Farm)』(1945年)
- 『1984年(Nineteen Eighty-Four)』(1949年)
『本屋の思い出』書店員時代のオーウェルをかいま見る
ジョージ・オーウェルは、1927年にビルマの警察を退職した後、作家を目指してロンドンとパリで生活していました。
特にパリでは、貧困生活を送りながら、そこでの体験が彼の初期の著作に強く反映されているといわれています。
今回、ジョージ・オーウェルをふと思い出すきっかけとなったのが、『ブックセラーズ・ダイアリー』という本です。
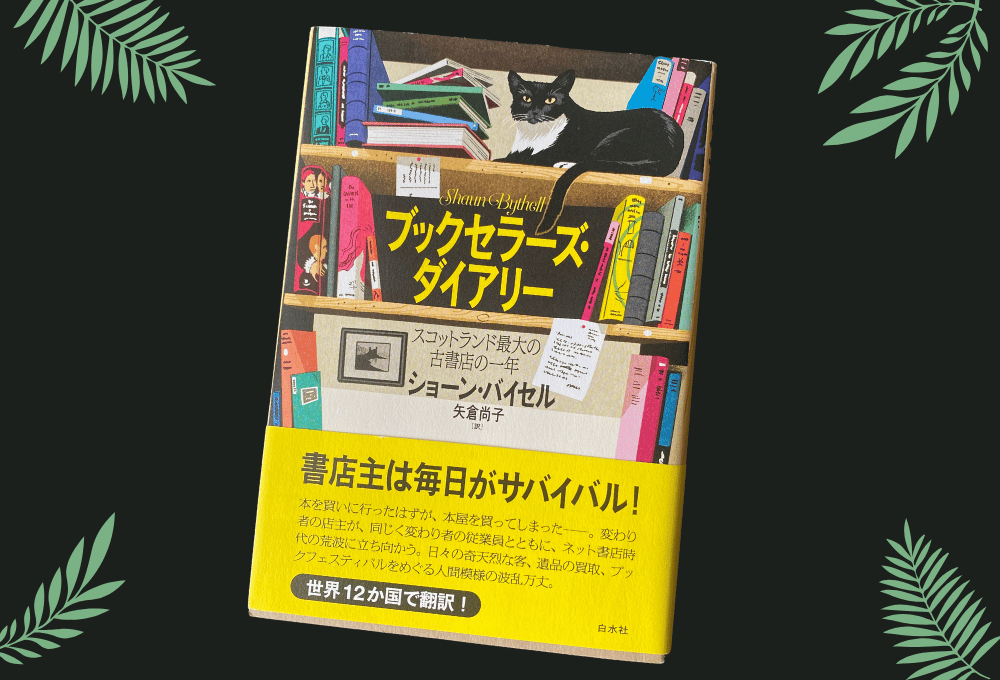
この本は、スコットランドのウィグタウンで古書店「ザ・ブックショップ」を営む著者ショーン・バイセルが、2014年から2015年にかけて本屋での日常を綴った日記形式のエッセイです。
ショーン・バイセルが古書店のオーナーになった経緯はとてもユニークで、『本を買うために訪れた書店を、そのまま本屋ごと購入してしまった』という話は、まさに『人生何が起こるかわからない』ということを感じさせられます。
ダイアリーの各月の冒頭には、必ずオーウェルのエッセイ『本屋の思い出』からの引用があり、オーウェルがロンドンの小さな本屋で働いていた頃に客を観察しながら考えていたことが、今のバイセルの考えと絶妙にリンクしていて、とても興味深いです。

そして、ジョージ・オーウェルが『動物農園』のような政治的風刺作品を書きつつ、もう一方では『本屋の思い出』のようなエッセイも執筆しているという事実に、改めて感慨深さを感じました。
心に残る寓話:オーウェルの『動物農園』を読んで
ジョージ・オーウェルの『動物農園』は、物語を読み終えた後も心に強い余韻を残す作品です。
登場する動物たちの姿を通して、権力や忠誠心、そして支配の恐ろしさが深く描かれています。
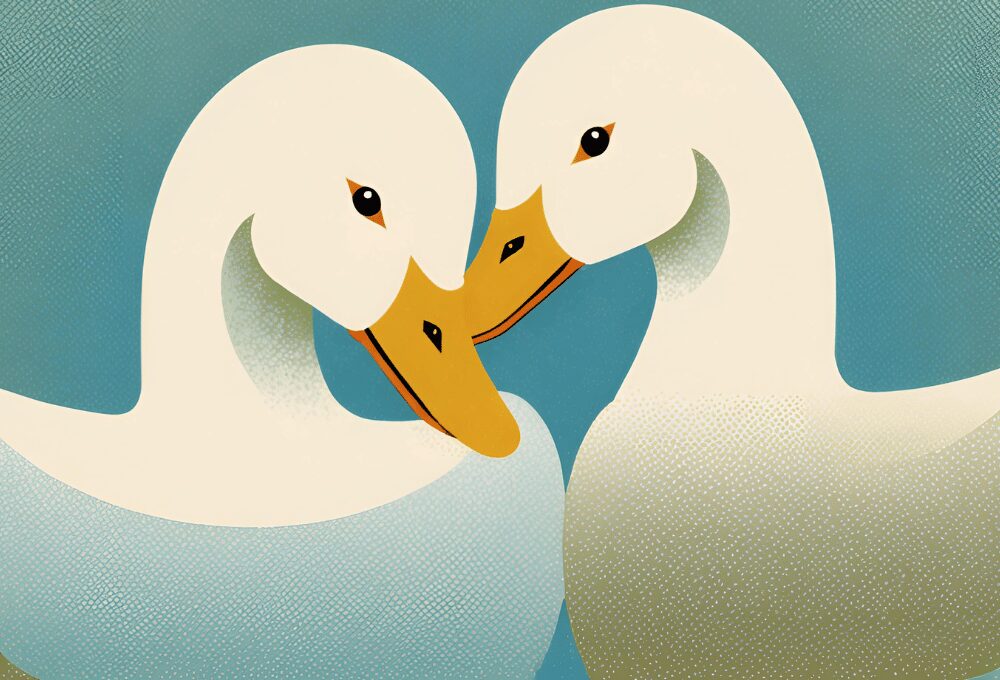
特に、ボクサーの生き方は「ただ従うだけでいいのか?」と問いかけてくるような強いメッセージを感じました。
また、挿画を担当されたヒグチユウコさんの動物たちは、物語の想像力をさらに掻き立て、物語の世界観をより深く楽しむことができました。















この作品は、風刺的な物語に興味がある方や、寓話を通して社会のあり方について考えたい方におすすめです