もし、誰かを深く想い続けることが「狂気」と呼ばれるなら、
私たちは、いったいどこまでなら正気のまま愛し続けることができるのでしょうか。
ニザーミーの叙情詩『ライラとマジュヌーン』は、
そんな問いを、まるで一編の祈りのように物語ってくれます。

愛とは何か。
それは手に入れることではなく、
ただ在り続けることだけでいいのかもしれない。
アラブの民間伝承に端を発し、
12世紀のペルシア詩人ニザーミーによって書き綴られたこの物語。
ここから『ライラとマジュヌーン』という物語の世界を、
すこしずつ、たどっていきたいと思います。
タイトル:『ライラとマジュヌーン』
著者:ニザーミー・ガンジャヴィー
翻訳:岡田恵美子
出版社:平凡社
もくじ
簡単あらすじ

物語の舞台は、まだ愛という言葉が今ほど軽々しく使われていなかった時代。
名家に生まれた少年カイスは、少女ライラに出会い、やがて心のすべてを彼女に捧げていきます。
けれど、彼の燃えるような恋心は、周囲には狂気と映りました。
家族や社会の価値観がふたりを引き裂き、
カイスは砂漠へとさまようようになります。
やがて人々はカイスを「マジュヌーン(=狂人)」と呼ぶようになりました。
ですが彼の愛は、ただの執着や哀しみではありません。
それは会うことさえ叶わなくとも、
ただライラを想い名前を呼びつづける
そういう祈りのような、まるで魂の静かな昇華のようでした。
ふたりが選んだ道の先に、いったい何が待っているのか。
マジュヌーンの一途な愛と、イスラム文化における唯一神の概念

マジュヌーン
この名前は、ペルシア語やアラビア語で「狂人」を意味します。
けれど、その言葉が指す狂気は、
単なる理性の喪失とは少し違い、どこか切なさや、敬意さえ感じる時があります。
マジュヌーンの愛は、ただひとりを想い続けるものでした。
その一途さには、どこか宗教的な祈りのような気配すら漂っています。
イスラム文化において大切にされる「唯一」という考え方
マジュヌーンがライラただ一人を愛しぬいた姿は、
「たったひとつの、唯一の存在に、すべてを捧げる」という強い想いが感じられます。
それは、もはやひとりの女性への恋を超え、
もっと深い、目に見えない何かに向かって心を差し出しているようにも見えるのです。
こうした在り方は、イスラムの神秘主義であるスーフィズムにも通じています。
スーフィーたちは、愛を通して自我を手放し、やがて神とひとつになることを目指します。
マジュヌーンの姿は、その道を歩む者の姿に、重ねられているのでしょう。
マジュヌーンの愛に込められた、いくつかの大切なこと
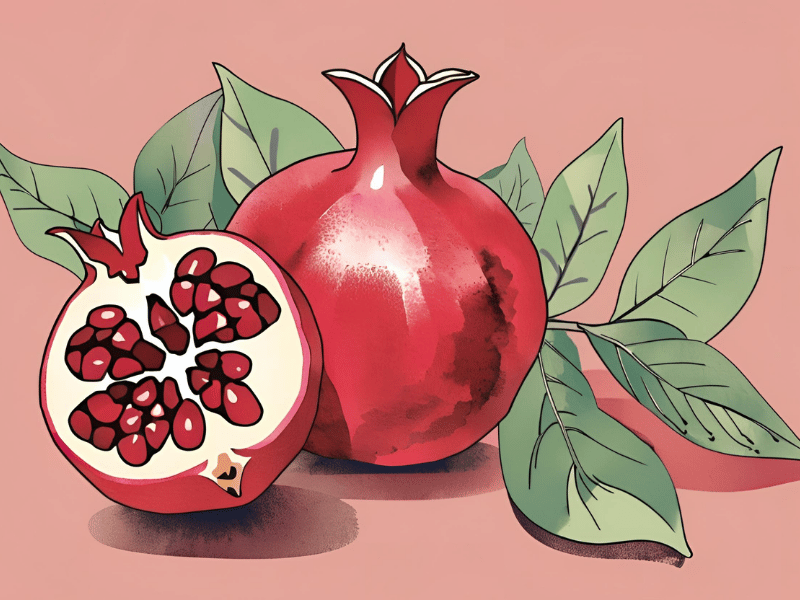
この物語は、
12世紀の詩人ニザーミー・ガンジャヴィーが、王侯の依頼を受けて書き上げた作品です。
アラブに伝わる口承の恋物語を、ニザーミーはペルシア語の叙事詩として再構築し、恋と哲学と精神性が溶け合う一篇の詩に昇華させました。
ここでいう「詩」とは
日本語でいう短い詩ではなく、
叙事詩(じょじし)=物語を語る長編詩のことです。
巻末の解説から、原典はペルシア語の韻文(リズムある言葉)で書かれた作品とあります。
登場人物の会話や情景描写も、すべてリズムや響きを大切に綴られているのでしょう。
日本語訳では
この物語は、読者が自然に味わえるように、散文のかたちで訳されています。
小説のようにすっと入ってくる言葉の中に、原詩のリズムや余韻がふっと顔をのぞかせる瞬間があり、それがとても心地よく響いてきます。
不思議な愛の美学
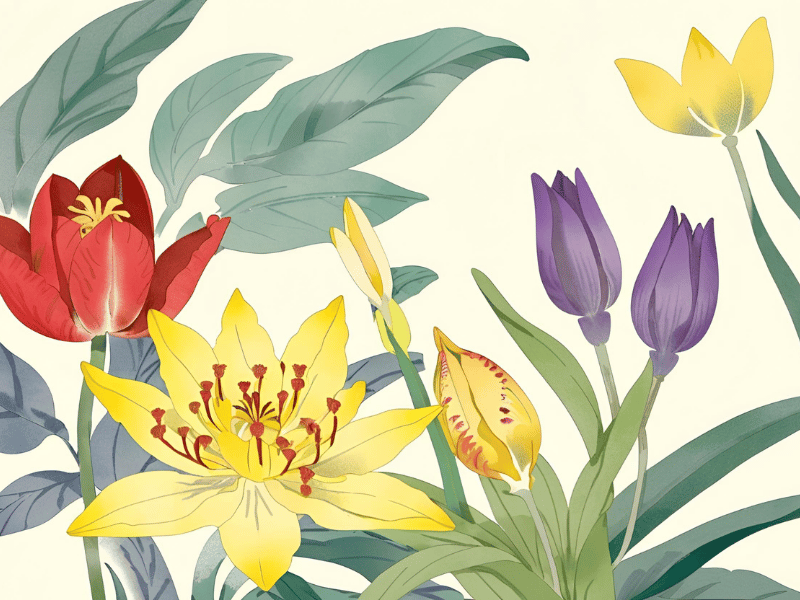
マジュヌーンの愛は、少し不思議です。
マジュヌーンはライラを愛しながらも、再会を望まず、
ただ名前を呼び、詩を捧げ、砂漠から想い続けました。
会いたい
触れたい
一緒にいたい
という気持ちは、恋にとってごく自然なもの。
でもマジュヌーンは、その願いを手放すことで愛を深めていくのです。
マジュヌーンの愛は、ライラと一緒に過ごすことを目的としていません。
ただ彼女がこの世に在ること
その存在を信じ
思い続けること
そうすることで、自分自身の生を燃やしていたように見えます。
それはまさに祈りに近い愛。
目に見えず、手に触れることもないけれど、心の中に確かに灯り続けるもの。
そんな愛のかたちが、この物語には描かれています。
多くの恋愛では、
ときに「手に入れる」「繋ぎとめる」といった方向に向かいがちです。
けれどマジュヌーンの愛は、
何かを得ようとするよりも、むしろ「自分の内にある想いを純粋に生き抜くこと」に重きが置かれていたように思います。
それは、「欲望の愛」ではなく「祈りの愛」
語り合ったり、そばにいることはないけれど、
だからこそ、どこまでも静かで、どこまでも深い。
とても真似のできる愛し方ではありませんが、
そんな愛があったというこの物語は忘れることができなくなりそうです。
クラプトンの「Layla」との意外なつながり
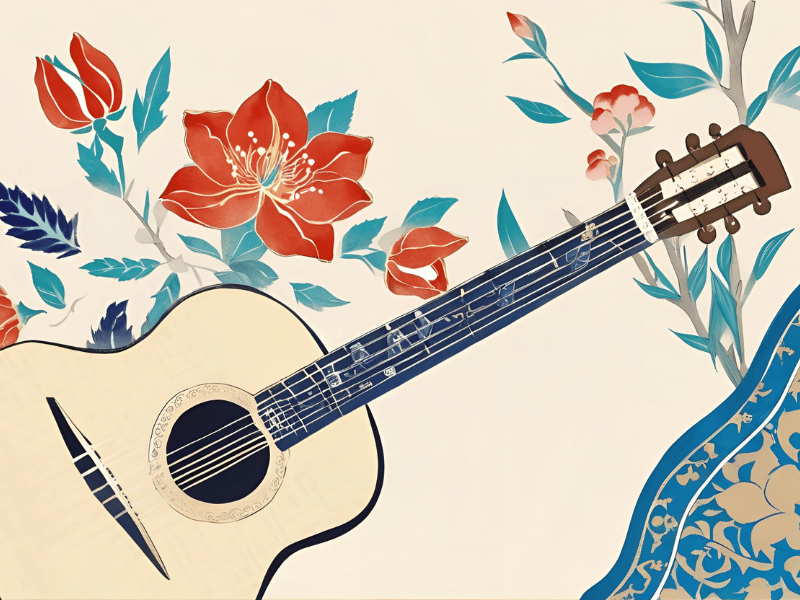
実はこの物語、エリック・クラプトンの名曲「Layla」の着想源にもなっているそうです。
愛してはいけない人を想い続ける気持ちに、クラプトン自身の想いが重なったのでしょう。
あのギターの音には、マジュヌーンの叫びがそのまま溶け込んでいるような気がします。
『ライラとマジュヌーン』を書いたニザーミーはどんな人?
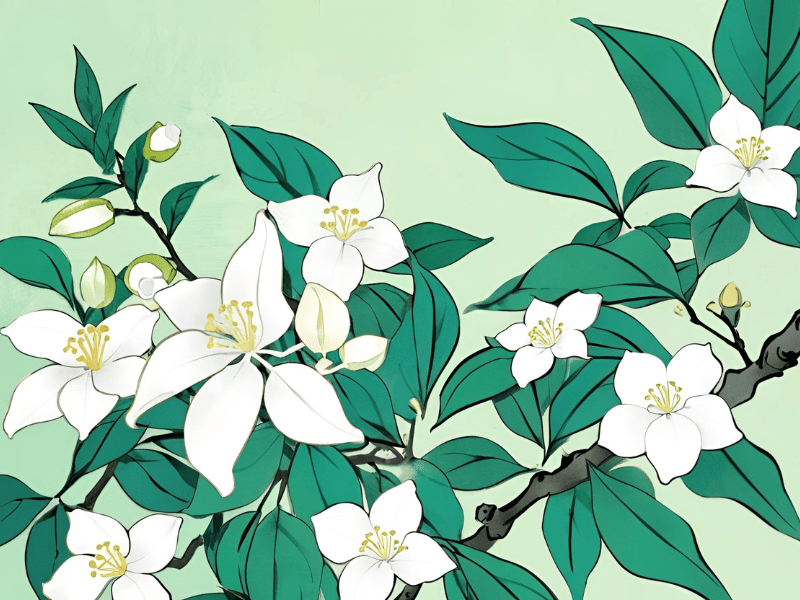
ニザーミー・ガンジャヴィーは、
12世紀のペルシアを代表するロマンス叙事詩人
- 1141年ごろ生〜1209年ごろ没
- 現在のアゼルバイジャンにあたる街・ガンジャ生まれ
宮廷詩人ではなかったものの、その詩才は多くの王侯たちに認められていました。
恋や哲学、人生の深い問いを、美しい言葉で綴ることに長けた詩人で、
なかでも、5つの長編叙事詩から成る作品集『ハムセ(五部作)』でよく知られています。
その中のひとつが、『ライラとマジュヌーン』
ニザーミーは、アラブ世界に伝わっていた悲恋の伝説をもとに、
ただの恋愛物語にとどまらない、魂の深い旅としての愛を描き出しました。
翻訳者の岡田恵美子さん
1932年東京生まれ
テヘラン大学博士課程修了
専攻はペルシア文学
訳書『ライラとマジュヌーン』他、『ホスローとシーリーン』
まとめ
愛は時に人を壊し、
時に、誰よりも美しくその人を照らします。
『ライラとマジュヌーン』は、
「何があっても消えなかった想い」の物語でした。

もし今、誰かに心を預けているのなら
その想いの先に、優しさが残るといいですね。

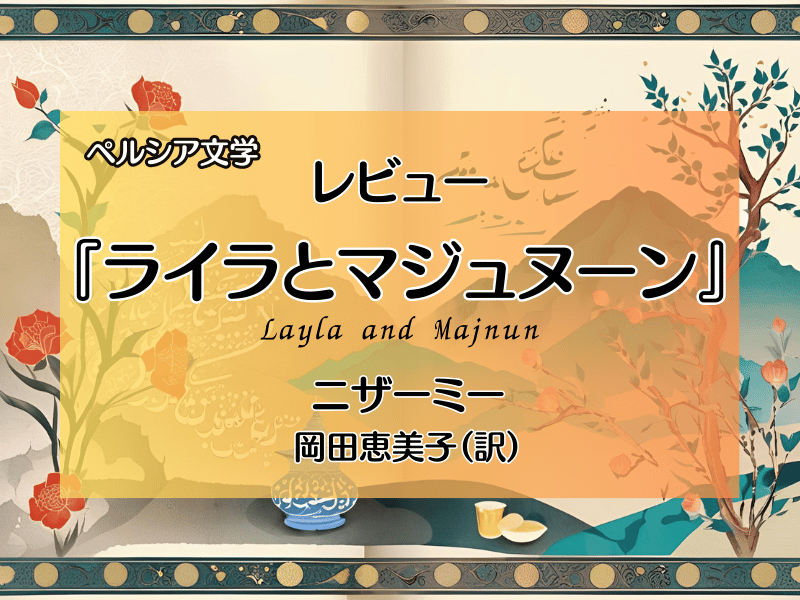
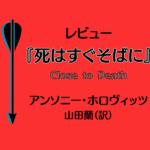




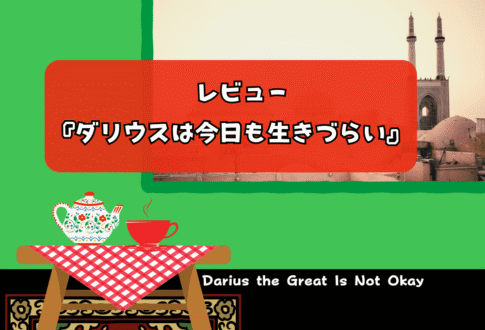
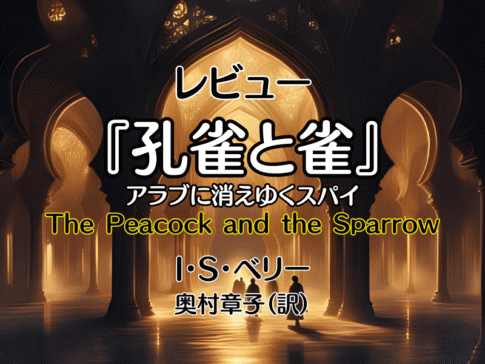




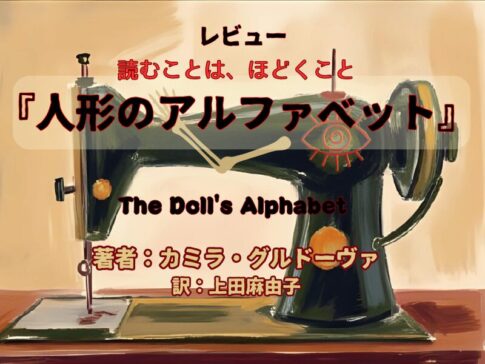
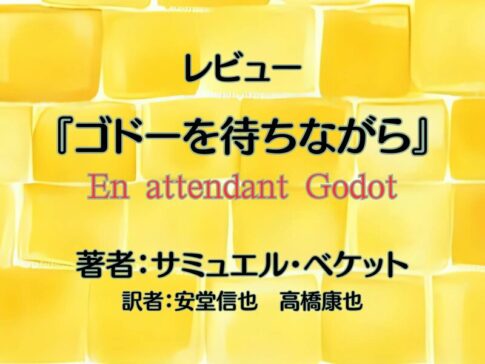
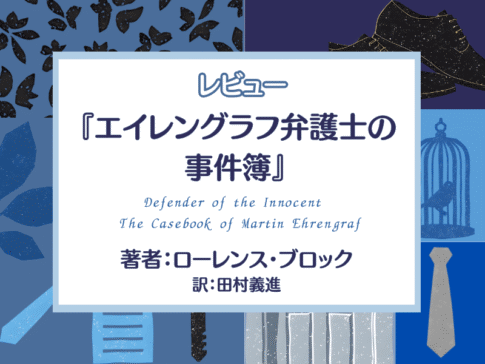
愛の狂気を味わってみたい方におすすめです