『そして誰もいなくなった』(原題:And Then There Were None) は、1939年、アガサ・クリスティが49歳のときに発表した作品で、名探偵ポアロもミス・マープルも登場しないノン・シリーズにあたる一作です。
この作品は以前、ドラマなどで観たことがありました。その時の記憶では、10人目の場面で「なぜ?」と違和感を覚えたことを今でもぼんやりと覚えています。
それから長い年月が過ぎ、最近になってまた少しずつクリスティ作品を読むようになり、改めてこの『そして誰もいなくなった』を読んでみたい気持ちが湧いてきました。

有名な作品だからこそ、昔観た映像の記憶と比べながら読むのも面白そうです。
ラストで感じたあの違和感――果たして今回は解消されるでしょうか?
それでは、この緊迫感あふれる物語を読み終えた感想を、ここから綴っていきたいと思います。
邦題:『そして誰もいなくなった』
著者:アガサ・クリスティ
翻訳:青木久惠
出版社:早川書房<クリスティー文庫80>
発行日:2010年11月15日、2017年2月15日(二十刷)
ページ数:387ページ
Title: And Then There Were None
Author: Agatha Christie
Publication Year: 1939
Category: Mystery, Closed-Circle Mystery, Crime Fiction
簡単あらすじ
孤島「兵隊島」に、10人の男女が見知らぬ主からの「招待状」を受けて集まる。
互いに面識のない彼らは、豪華な邸宅での滞在を楽しむはずだった。
だが夜になると、録音された声が部屋に響き渡り、全員の「過去の罪」が暴露される。
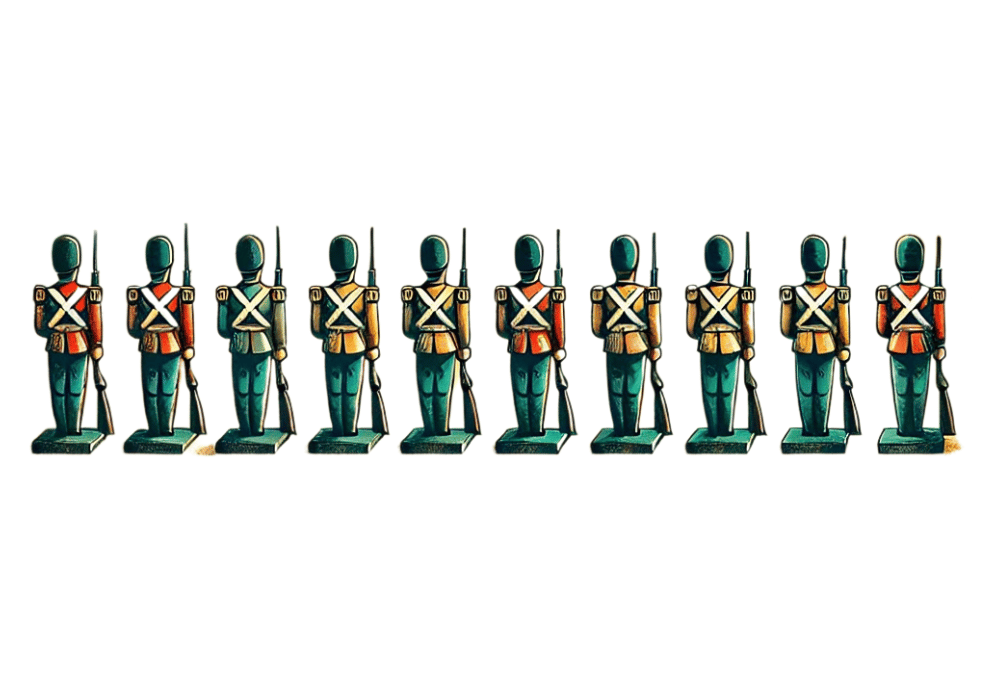
その日から、童謡「十人の兵隊さん」の歌詞通りに、彼らは次々と命を落としていく。
犯人はこの中にいるのか、それとも別にいるのか。
衝撃的な結末が待つ、緊迫のミステリー。
見知らぬ主からの招待状を信じて島にやってきた理由を考察
ことの始まりは「見知らぬ主からの招待状」が届いたことから始まります。
ある日、はっきり断定できない曖昧な人物から島への招待状が届いたら、果たして行く気になるでしょうか?普通なら、怪しすぎて無視するところですよね。特に、現代であれば。

ですが、この物語の舞台は1930年代。
手紙が主要なコミュニケーション手段だった当時では、招待状そのものをそこまで疑う文化がなかったのかもしれません。
とはいえ、彼らも全く疑わなかったわけではなく、一度は「本当に行って大丈夫だろうか?」と考えたことでしょう。
それでも最終的に「行く」という判断を下した理由は何だったのでしょうか?

それは招待状の内容が巧みだったというしかありません。
招待主は、一人ひとりに対して個別に「あなたに特別な理由がある」と思わせる文面を用意していました。
それぞれが自然に受け入れてしまうような巧妙な誘い文句が、警戒心を和らげたのでしょう。
こうして少しずつ、足音を立てて“And Then There Were None”(そして誰もいなくなった)へと向かっていくあたりがさすがだなと思いました。
孤立感を生む「孤島」という舞台設定
今回舞台となった「兵隊島」のような孤島(クローズド・サークル)が生み出す効果には、次のようなものがあります。
逃げ場がない孤立感
どこにも行けない状況が、登場人物たちを強烈な不安に追い込みます。
犯人はその中にいるという緊張感
疑心暗鬼が増幅され、人間関係が徐々に崩れていきます。
心理的な諦めの芽生え
最初は「自分が死ぬはずない」と信じていても、次第に「どうせ逃げられない」という絶望感が漂い始めます。
この小説は、死そのものの恐怖ではなく、人間が極限状況でどのように精神的に追い詰められていくかを描いているように感じました。

孤島という閉鎖的な舞台だからこそ、こうした心理の揺れがリアルに浮かび上がります。
また、ぼんやり覚えていたラストの違和感も、今回改めて読んでみることで解消されました。まさか、あの結末にそんな理由が隠されていたなんて!
小説のほうも読んでみて良かったと思える一冊でした。
まとめ
『そして誰もいなくなった』は、孤島で人が次々に姿を消していく緊張感あふれる展開に加え、「人間の罪と罰」や「正義と狂気の境界」といった深いテーマも描かれた作品です。
長すぎず、テンポよく進む物語なので、気軽に読み始められる一冊ですよ。
















探偵が出てこないノン・シリーズもたまにはいいですね