ペルシアの風にゆれる、ひとひらの四行詩。
たった四行のなかに、宇宙がある。
「いまを楽しめ」「あしたのことは知らなくていい」
千年もの昔、ペルシアの詩人ハイヤームが語りかけたことばです。
それは、いまを生きるわたしたちにも、ふとした瞬間にそっと寄り添ってくれます。そんな詩を集めた一冊、それが『ルバイヤート』です。

この『ルバイヤート』という詩集を手に取ったのは、
『ダリウスは今日も生きづらい』 という小説との出会いがきっかけでした。
これはアメリカに暮らすイラン系少年の物語です。

その物語を通して、イラン(ペルシア)の文化や歴史に興味を持ち、
続けてペルシア文学の『ライラとマジュヌーン』を知りました。

さらに杉森健一さんの『ペルシア文化が彩る魅惑の国イラン』を読み進めるなかで、紹介されていた4人の詩人の名前と作品をメモして、本屋さんをのぞいてみました。

4人の詩人は
フェルドウシィー
ハイヤーム
サアディー
ハーフェズ
いちばん最初に目にとまったのが
ハイヤームの『ルバイヤート』
そんな流れで、この詩集にも手を伸ばしてみることになりました。
ではさっそく、『ルバイヤート』を読んで、心に残ったことを少しだけ綴ってみたいと思います。
『ルバイヤート』
著者:オマル・ハイヤーム
翻訳:小川亮作
出版社:岩波書店/岩波文庫
ページ数:173ページ
出版日:1949年第1刷、1979年第23刷、2020年第78刷
Title: RUBĀʿIYĀT
Author: ʿUmar Khaiyām
もくじ
ハイヤームとはどんな人?
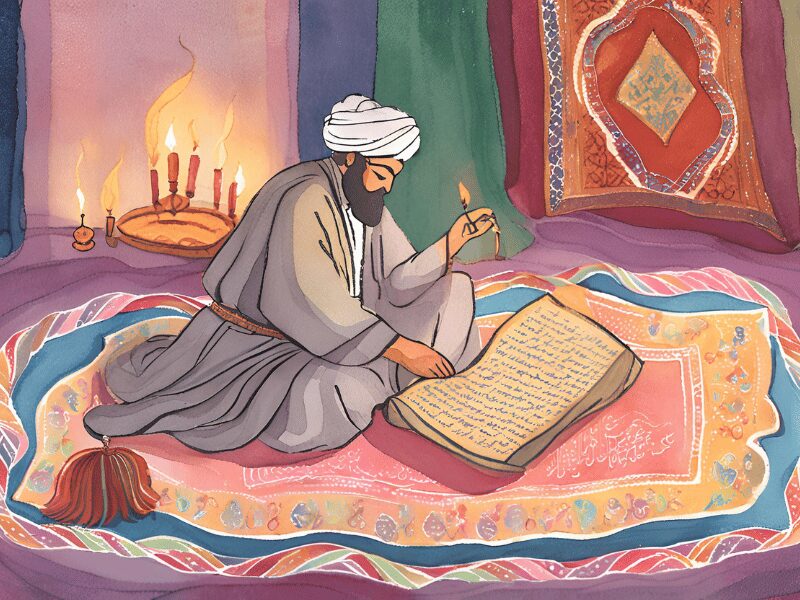
『ルバイヤート』を書いたオマル・ハイヤームは、
11世紀のペルシア東部・ネイシャプール(Nishapur)現在のイラン北東部生まれ。数学者であり、天文学者であり、そして詩人です。
ハイヤームがこの詩を書いたのは、今からおよそ千年前
セルジューク朝時代のペルシア(11世紀後半から12世紀前半)
日本ではちょうど平安時代の終わりから鎌倉時代のはじまり、
ヨーロッパでは十字軍遠征が行われ、
西洋美術ではロマネスク様式が花開いていました。
世界のあちこちで、大きな変化の波が動いていた時代です。
ハイヤームは、数学では特に代数学や幾何学で大きな業績を残し、
天文学者としては暦の改良にも関わったことが知られています。
そんな理知的な仕事をしながら、詩の世界では、
「人生ははかなく、明日のことは誰にもわからない」
「だからこそ、いまこの瞬間を楽しもう」
そんな思いを、四行の短い詩にこめて綴っていきました。
そして神や運命についてもどこか懐疑的で、
「ほんとうのことは誰にもわからないのでは?」
と問いかけるようなところがあります。
その問いかけは深刻すぎず、どこかユーモアを感じさせる。
たった四行の詩。
けれどその意味は読む人の心の数だけ、いく通りにも変わっていくのだと思います。
ペルシアの詩を世界にひらいた詩人はだれ?

その詩人とは
エドワード・フィッツジェラルド
Edward FitzGerald|1809–1883
イギリスの詩人・翻訳家
『ルバイヤート・オブ・オマル・ハイヤーム』の英訳者として世界的に有名
小さな奇跡のはじまり
- 1853年、オックスフォード大学でエドワード・カウエルからペルシア文学を学び始める
- カウエルがカルカッタのアジア協会図書館でハイヤームの四行詩集を発見
- この写本をフィッツジェラルドに送る
- フィッツジェラルドはハイヤームの詩に惹かれ、英語訳に挑み始める
- 1859年、無名で『ルバイヤート』初版(75詩)を自費出版
- 当初は注目されず、本屋の片隅へ
- それでも、詩人ロゼッティやスウィンバーンらの手によって、しだいに世界中へ広まっていった
もし彼がいなかったなら
もしカウエルが、あの詩集を発見していなかったら。
もしフィッツジェラルドが、この詩に心を寄せなかったら。
ハイヤームの言葉に私たちが出会うこともなかったかもしれません。
『ルバイヤート』は、まさに奇跡のように、時を越えて私たちに届けられた詩集なのです。
『ルバイヤート』を日本に届けた人たち
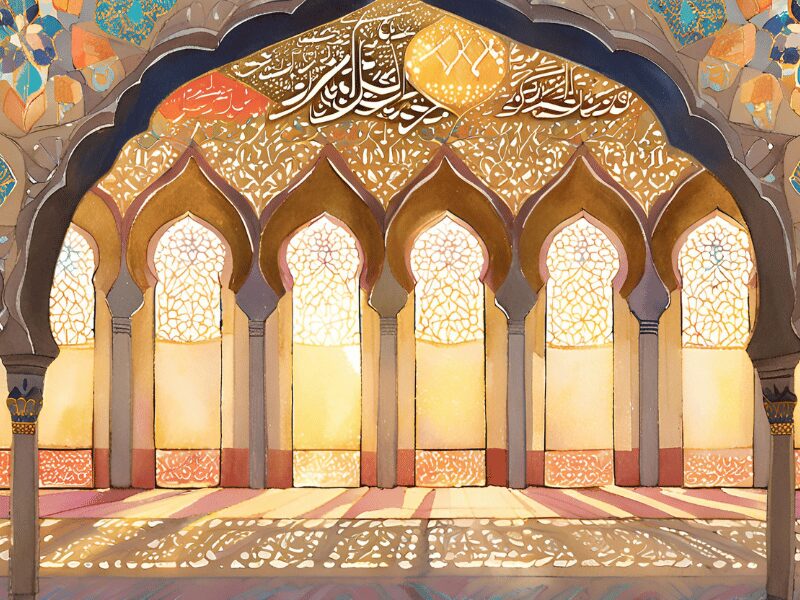
『ルバイヤート』を最初に日本に紹介したのは
明治時代の詩人、蒲原有明(かんばら ありあけ)
- フィッツジェラルドの英訳をもとに『有明集』(明治41年)に訳詩を収める
- 後に『有明詩集』(大正11年)としてまとめられる
こうして『ルバイヤート』は日本でも少しずつ知られるようになりました。
現在手に取る岩波文庫版(2020年第78刷)は、
小川亮作さんによる、より親しみやすい口語体の訳にあらためられた一冊です。
誰かがつないでくれたから、こうして今、ページをめくることができるのですね。
タイトルの『ルバイヤート』の意味は?
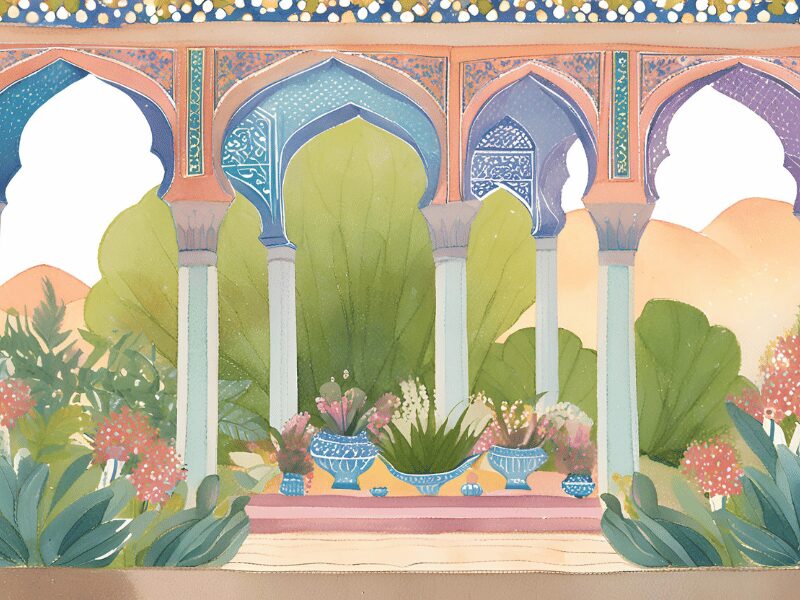
『ルバイヤート』はペルシア語で「四行詩の複数形」を意味します。
1つの四行詩は「ルバーイイ」と呼ばれます。
- ルバー=4
- ルバーイイ=4行詩
- ルバイヤート = その複数形
つまり、『ルバイヤート』は「四行詩の詩集」という、わかりやすいタイトルなのです。
すごくシンプルだったんですね。
チューリップの花がたびたび出てきます

4行の中には、哲学や皮肉、人生の真理がさらりと込められていて、
どの章から読んでも、それぞれの詩がひとつの宇宙のように立ち上がってきます。
そんな中で、よく目にした言葉のひとつが「チューリップ」でした。
なんだか意味ありげで気になって、ちょっと調べてみたところ、
チューリップは イランの国花 なのだそうです。
原産は中央アジアからペルシア、トルコにかけて。
ヨーロッパに渡ったのは16世紀以降といわれています。
とくに「赤いチューリップ」は、殉教や自由、犠牲を象徴する花として知られ、
イランでは革命や詩の中にもたびたび登場する存在だとか。
そんな背景を知ってから読み返してみると、
詩のなかにさらっと出てくる「チューリップ」という言葉にも、どこか静かな情熱や、はかない希望のようなものがそっと込められているように感じました。
印象に残った詩

『ルバイヤート』は、目次を眺めるだけでも、どこかこちらに語りかけてくるものがあります。
章タイトル
- 解き得ぬ謎
- 生きのなやみ
- 太初(はじめ)のさだめ
- 万物流転
- 無常の車
- ままよ、どうあろうと
- むなしさよ
- 一瞬(ひととき)をいかせ
最初ははじめの章から読もうと思っていたのですが、「ままよ、どうあろうと」という章のタイトルに目がとまり、思わずそのページをめくってみることにしました。
その中で特にいいなと思ったのが、次の一編です。
初めから自由意志でここへ来たのではない。
あてどなく立ち去るのも自分の心ではない。
酒姫よ、さあ、早く起きて支度をなさい。
この世の憂いを生の酒で洗いなさい。
この詩から感じたことは
ハイヤームは「生きる意味」を一生懸命に探そうとはしていない。
むしろ「意味を求めすぎることこそ、人生を苦しくしているんじゃない?」
と、肩の力を抜かせてくれるような感じがします。
「人は生まれてくる前に目的を決めてきた」
「両親さえ自分で選んで降りてきた」
そんなふうに語られる考え方もありますが、
ハイヤームのこの詩はそれとはどこか正反対。
生きる意味を重たく問い詰めるのではなく、
「だからこそ、今この瞬間を自分なりに楽しんでみようよ」
と、軽やかに背中を押してくれている気がします。
意味や使命に縛られすぎずに、今日を生きる。
そんな生き方も、ひとつの知恵なのだと教えてくれる詩でした。
まとめ|この詩集がくれたもの
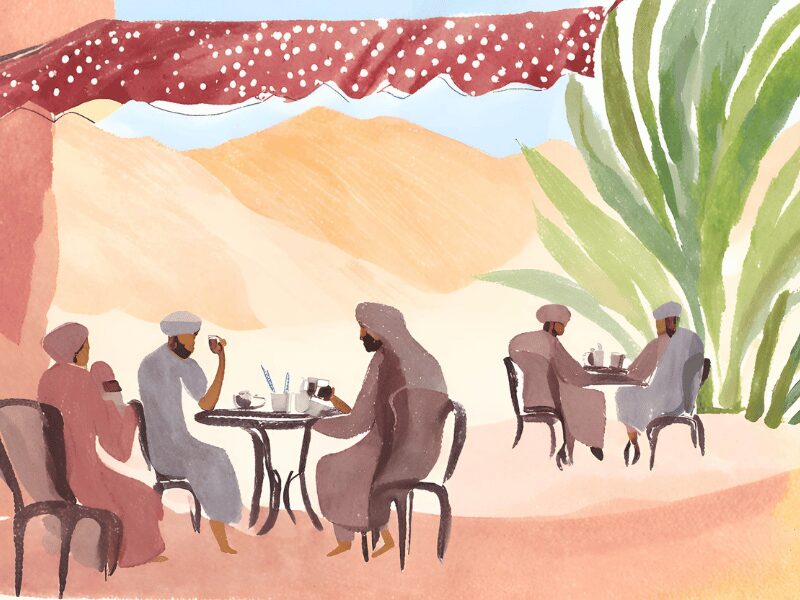
『ルバイヤート』を読み終えて、心の中に静かに広がったものがあります。
それは
「すべてを知ろうとしなくていい」
「ただ、今ここにいることを楽しんでいい」
という、存在そのものを祝福するやさしい感覚。
千年という大きな時間の流れに、そっと身を任せたからかも知れません。


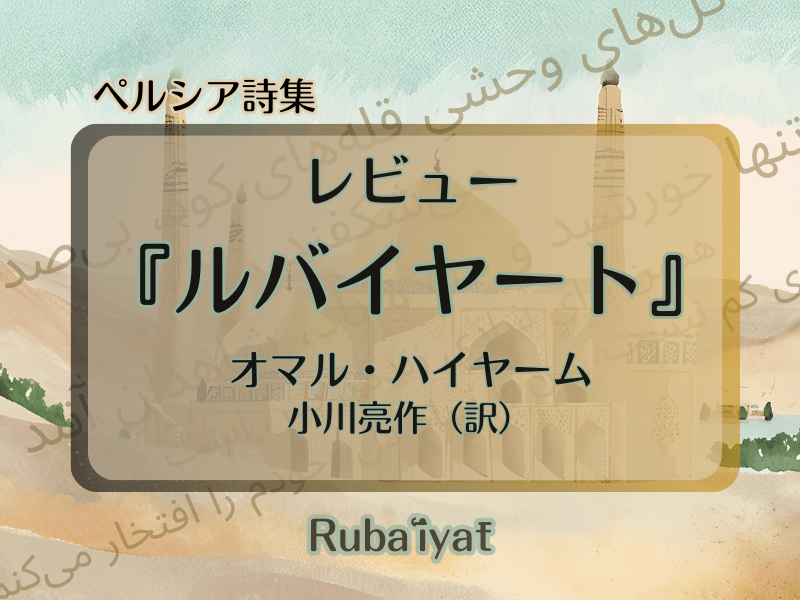

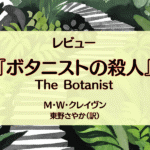
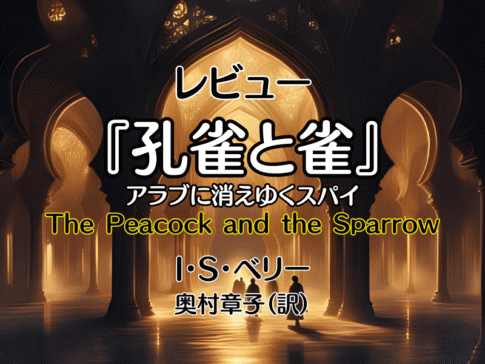
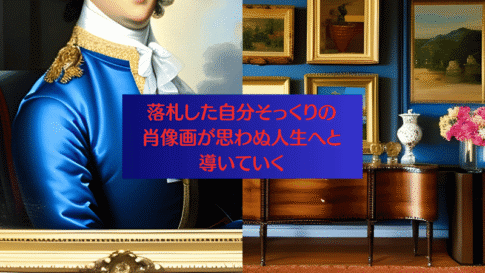
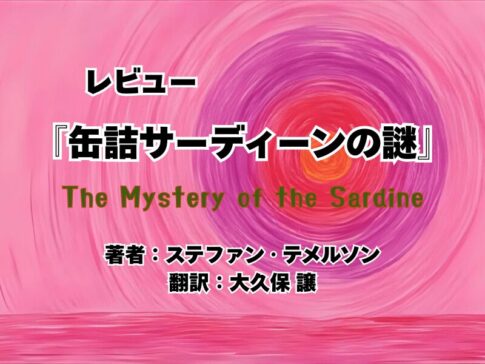


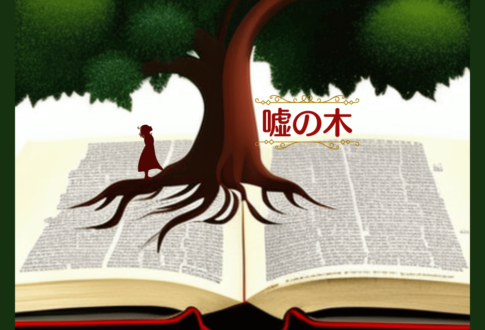

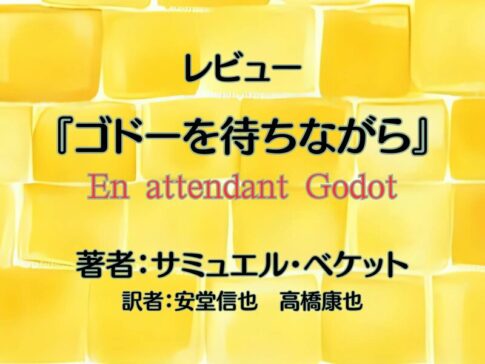

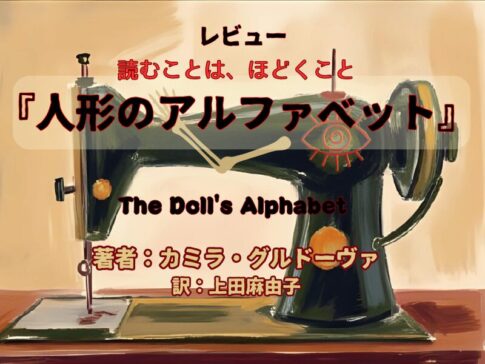
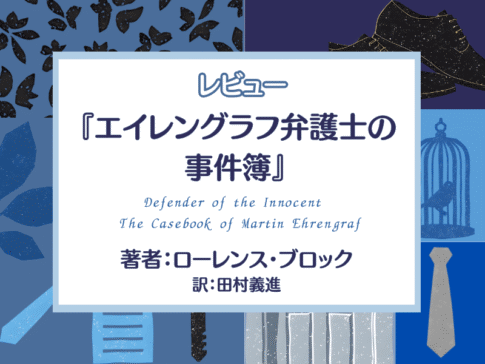
ぜひ、4行の宇宙をお楽しみください