無実の人を救うこと。
それが、弁護士という仕事の根っこにある想い。
けれど、その想いを少しだけねじれた形で貫く男がいる。

ローレンス・ブロックの『エイレングラフ弁護士の事件簿』は、
決して敗訴することのない弁護士を描いた短編集です。
絶対に「有罪」にさせない。
それがエイレングラフの流儀。
でも、その流儀は・・・
はっきり書かれているわけではないけれど、
読み進めていくうちに、ふと疑ってしまう。
この弁護士は、裏で誰かに罪をなすりつけて無罪を勝ち取っているのではないか。
そんな疑いが、強く頭から離れなくなる。
そして短編を一つ、また一つと読み進めるうちに、その疑いは静かに確信へと変わっていく。
本書は、犯罪小説の巨匠ローレンス・ブロックが1976年から書き継いできた連作十二編を収めた短編集。
それではここから、感想を綴っていきたいと思います。
タイトル:『エイレングラフ弁護士の事件簿』
著 者:ローレンス・ブロック
訳 者:田村義進(たむら よしのぶ)
発行日:2024年9月10日
出版社:文藝春秋(文春文庫)
ページ数:366ページ
Title: Defender of the Innocent – The Casebook of Martin Ehrengraf
Author: Lawrence Block
Country: U.S.A.
Genre: Crime Fiction / Short Story Collection
もくじ
どんな一冊?
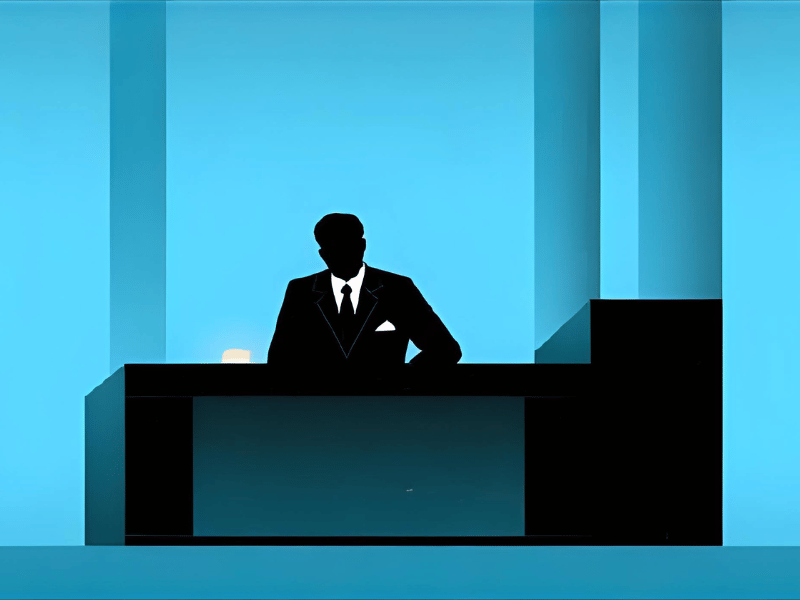
ローレンス・ブロックが描く弁護士マーティン・H・エイレングラフは、依頼人を「助ける」弁護士です。
ただし、その「助け方」は、必ずしもまっとうとは言えません。
各エピソードは、トラブルに巻き込まれた依頼人とエイレングラフの会話を軸に進んでいく構成。
- 形式:法廷ミステリ/心理サスペンス寄り
- トーン:簡潔で静か、どこか上品
- 長さ:短編連作で読みやすい(寝る前に1話タイプ)
いわゆる「犯人当て」の推理ではなく、
「いかにも有罪」な依頼人をどうやって「無罪」にしていくか。
そしてその結果、どんな代償が生まれるのか、そこが本作の読みどころです。
エイレングラフの形式美|詩編

この事件簿の特徴のひとつに、
各エピソードの冒頭に置かれる一篇の詩(ポエム)の存在があります。
どうやらこれは、エイレングラフ自身が詩をこよなく愛する人物だからのようです。
登場する詩人は、
トマス・グレイやウィリアム・ブレイク、
シェイクスピアやスウィンバーンなど、古典から近代にかけての名だたる面々。
その使われ方には強弱があり、
前面に出る詩もあれば、下地として物語全体のトーンを支える詩もある。
個人的には、ウィリアム・ブレイクの初期作品、
『無垢の歌』『経験の歌』を絡めた話が心に残りました。
エイレングラフの戦略的美意識|ファッション編

エイレングラフの報酬は、依頼人が無罪になったときだけ支払われる「成功報酬」制。
その額は、常識では考えられないほどの桁外れな金額。
でも、もし敗訴すれば、一銭も受け取らない。
まさに結果がすべてという契約です。
そして、彼は戦略的に装いを計算し、
いつも上質なスーツに身を包み、髪型から靴の艶まで完璧に整える。
なぜそんな計算された装いが必要なのか。
それは、依頼人の心が移ろいやすいことを知っているから。
依頼人の多くは、罪に問われているときは
「いくらでも払います」と必死にすがるのに、
いざ無罪が決まると、その金額を渋り始める。
でも、彼らが渋るにも、一応の理由はあります。
エイレングラフの仕事ぶりは、
法廷に持ち込むことなく、水面下で動くことが多い。
そのため、依頼人の目には、彼が何をしたのかが見えないまま、真犯人が捕まってしまう。
まるで、犯人が突然降ってきたかのように。
だからこそ、彼は、支払いを渋る依頼人の心理を熟知している。
そして、彼にとっての隙のないファッションは、
「まあ、こんなにブランド志向なら、報酬が桁外れでも当然か」
と思わせるための、視覚的な武器。
それでも
時にはケチられてしまうのが、また面白いところです。
印象に残った一話|「エイレングラフの経験」
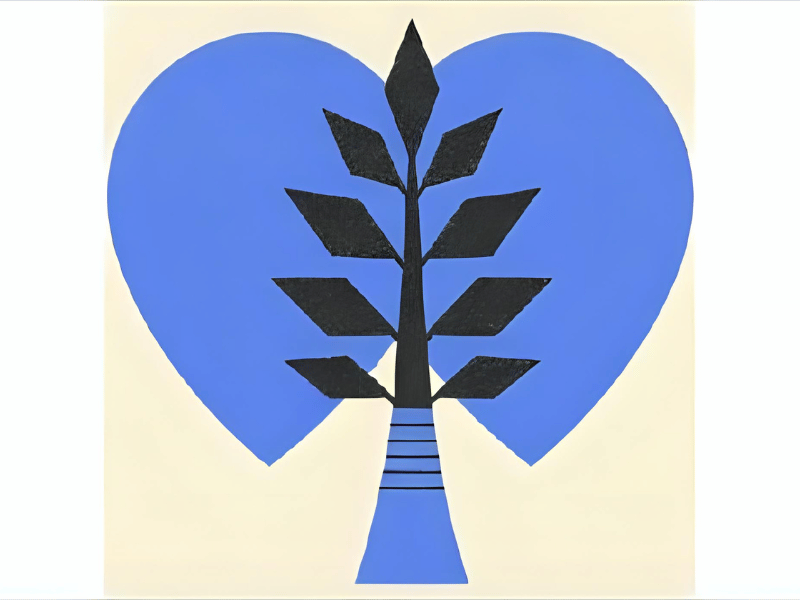
第三話「エイレングラフの経験」は、特に心に残ったお話です。
冒頭に引用されているのは、ウィリアム・ブレイクの詩。
『無垢の歌』『経験の歌』に見られるような、
純粋さと痛みの対比がこのエピソードの軸になっています。
ブレイクにとって「無垢」とは、世界をまだ知らない清らかさの象徴。
けれど同時に、外の世界ではとても危ういものでもある。
善人であることが、必ずしも良いとは限らない。
むしろ、悪意や策略を知らないからこそ、罠に落ちてしまうこともある。
そして、作中に印象的に出てくる一節。
切られた虫は鋤を許す
The cut worm forgives the plow
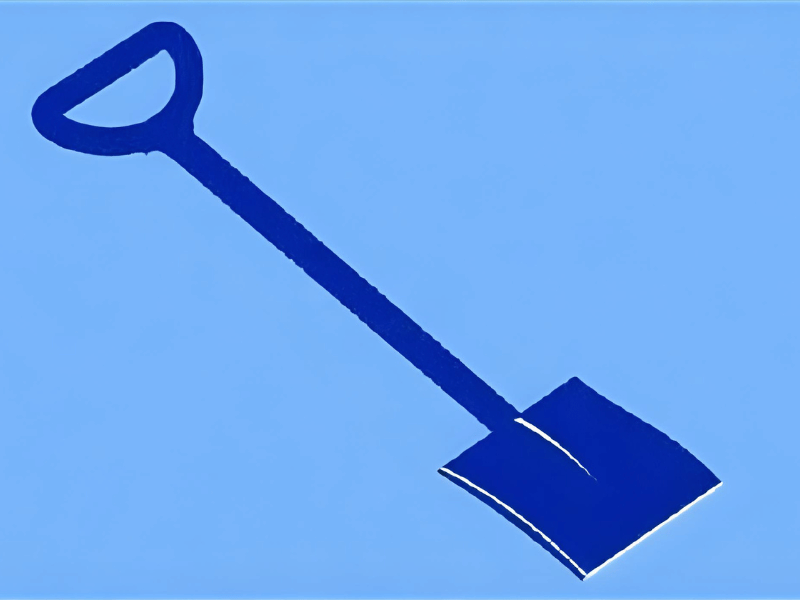
畑を耕す鋤の刃に切られた虫が、それでも鋤を恨まずに受け入れる。
そんな意味の詩です。
傷つけられても、世界を憎まない。
痛みを通して、ただそこに生きている。
この詩の一行が、物語の背景に静かに響いています。
痛みを受ける者(無垢)と、その痛みから学ぶ者(経験)
エイレングラフは、まさに経験の側に立つ人。
痛みを通して世界の仕組みを知り、
それを冷静に使いこなして生きている。
彼にとっての「善」は、正しさよりも現実を見抜く力に近い。
そして、その力こそが彼の「経験」なのだと思う。
読んでいると、少し胸がざわつく。
でも同時に、どこか納得してしまう自分もいる。
無垢なままでは守れないものがあって、
経験を積むことでしか見えてこない優しさもある。
そんなことを、考えさせられる一話でした。
著者紹介|ローレンス・ブロック(Lawrence Block)

ローレンス・ブロック(Lawrence Block)
1938年、アメリカ・ニューヨーク州バッファロー生まれ。
60年以上にわたり、推理・犯罪小説の第一線で活躍してきた作家です。
代表作に、
元アルコール依存症の私立探偵マット・スカダーを描くシリーズ、
陽気な泥棒バーニー・ローデンバー作品などがあり、
どちらも犯罪を通して人間を描く筆致に定評があります。
エイレングラフ弁護士シリーズは、彼の中でも異色。
暴力や事件そのものよりも、法と倫理のグレーゾーンを描いた知的な短編集です。
こんな方におすすめ
こんなかたに楽しんでいただける一冊だと思います。
- 一話ごとに完成された短編を味わいたい人
- 論理や計算の裏に潜む人間の矛盾を感じたい人
- 正義とは何か、善とはどこまでが善なのか。そんな問いを考えるのが好きな人




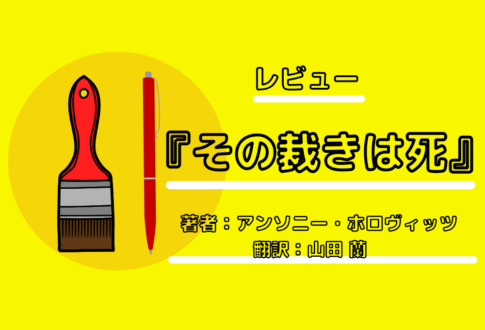
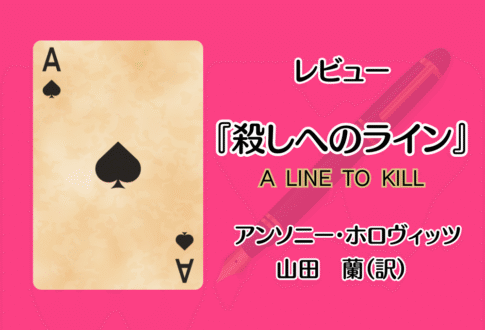
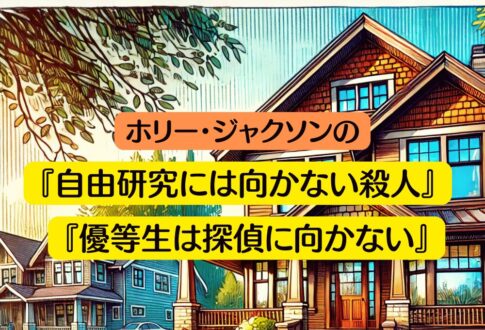
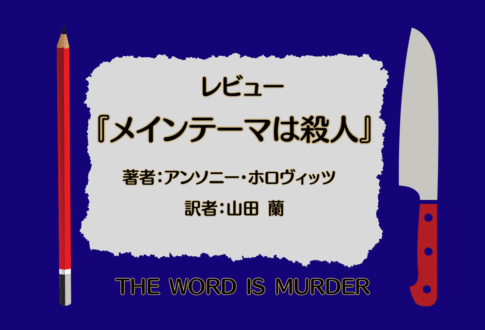
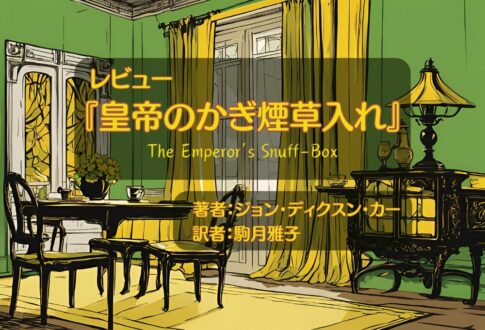
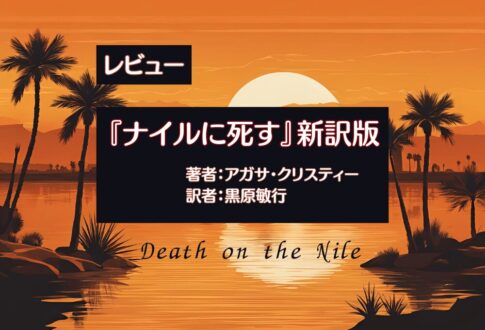
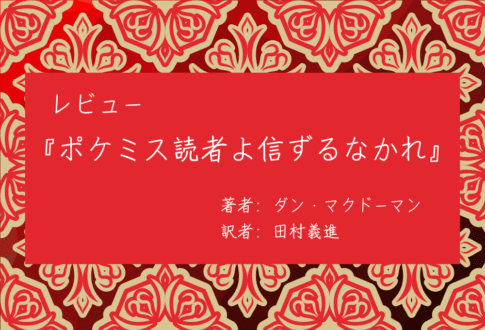
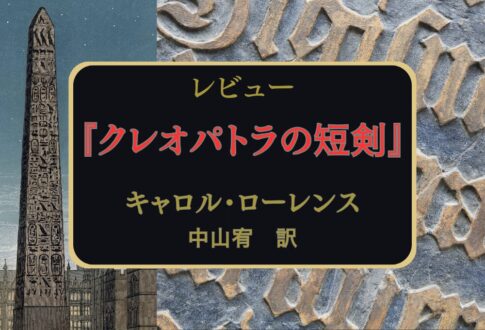
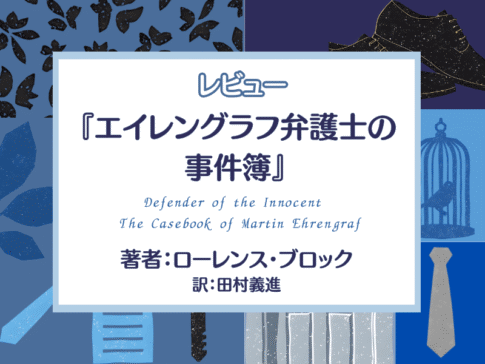
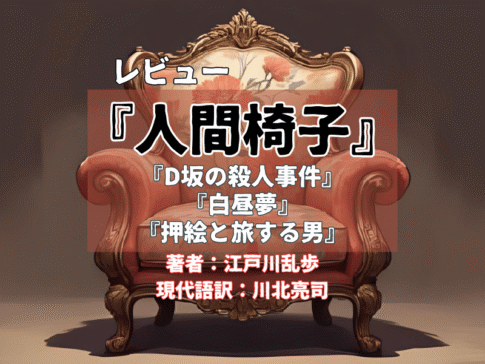
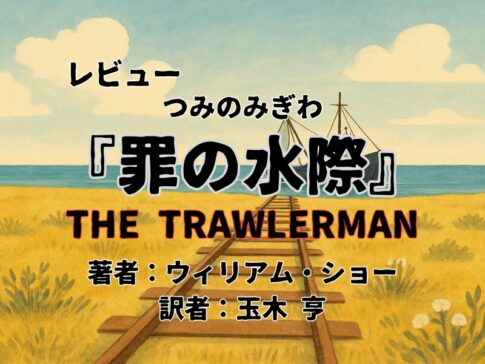
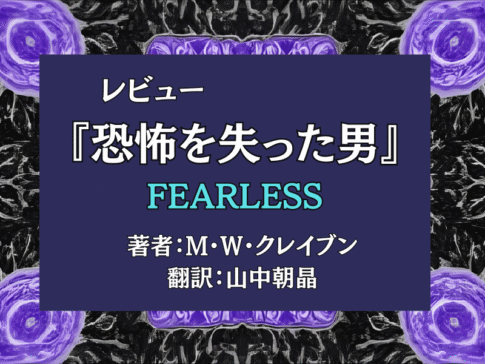
夜の読書や、コーヒー片手に一話ずつ読むのにぴったりの作品です!