サミュエル・ベケットの戯曲『ゴドーを待ちながら』は、
不条理劇というジャンルを代表する作品です。

と聞くと、
なんだか難しくて暗い話を想像してしまいます。
けれど実際に読んでみると、
意外にも軽やかで、どこかコントのようなテンポの良さがありました。
登場人物は五人だけ。
ほとんどの場面は、
ヴラジミールとエストラゴンという二人の男が、
どこかの道端でゴドーという人物をひたすら待ち続けるだけの話です。
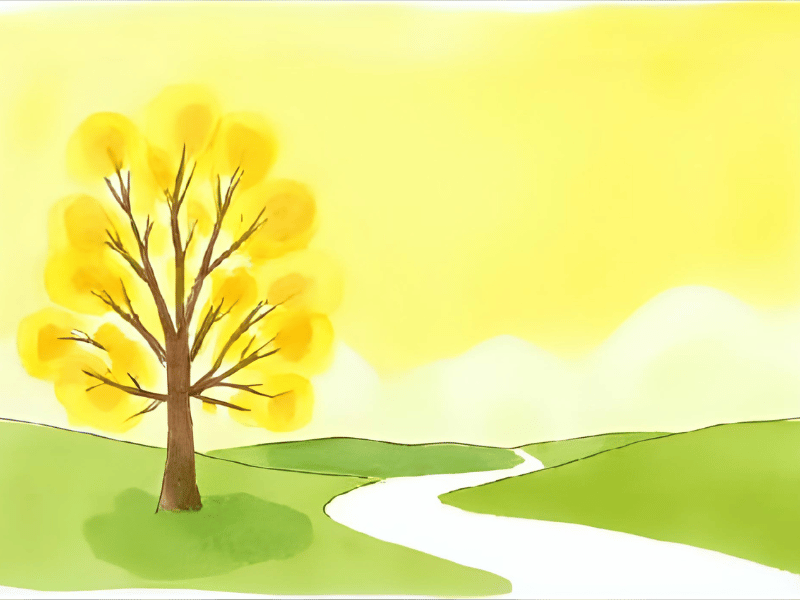
この二人の会話は、まるで漫才の掛け合いのよう。
噛み合っているようで噛み合っていない、
ちょっとした勘違いや愚痴が続き、どこか笑えてしまいます。
けれど、その笑いの奥には、
どんなに意味がなくても人が何かを続けようとする姿、
つまり「生きようとする力」が感じられます。
彼らは「待つ理由」をはっきり持っているわけではありません。
それでも「明日も来よう」と言い合い、去っていく。
その繰り返しが、可笑しみをおぼえてくる。
もう、ツボに入って笑わずにいられない。
普通なら「来ない人を待ち続ける」なんて無駄なことに思えます。
けれどこの作品を読んでいると、
「無駄に見えても、何かを待ちながら生きてもいい」
と、そんな気づきが、心に残ります。
希望とは、手に入れるものではなく、
待ち続ける姿の中にあるのかもしれません。
ベケットの描く不条理は、
絶望を語るためのものではなく、
むしろその中にある人間のユーモアや優しさを、
そっと浮かび上がらせるための舞台装置のように感じました。
サミュエル・ベケットの戯曲『ゴドーを待ちながら』は、

何も起こらないのに、なぜか心が動く。
私にとってはそんな不思議な作品でした。
サミュエル・ベケットと書籍紹介
サミュエル・ベケット(Samuel Beckett, 1906–1989)
アイルランド・ダブリン生まれの作家・劇作家。
若い頃にフランスへ渡り、パリを拠点に創作活動を行いました。
英語とフランス語の両方で執筆し、代表作『ゴドーを待ちながら』はフランス語で書かれています。
ベケットは「不条理劇」と呼ばれる文学潮流の中心的存在で、
何も起こらないように見える日常の中に、人間の孤独や希望を描き出しました。
その独特のユーモアと哲学的な視点が高く評価され、
1969年にはノーベル文学賞を受賞しています。
書籍紹介
タイトル:『ゴドーを待ちながら』
著者:サミュエル・ベケット
訳:安堂信也 高橋康也
出版社:白水社(白水Uブックス)
発行日:2013年6月10日
ページ数:227ページ
Original Title: En attendant Godot
Author: Samuel Beckett
Genre: Absurdist Drama / Play

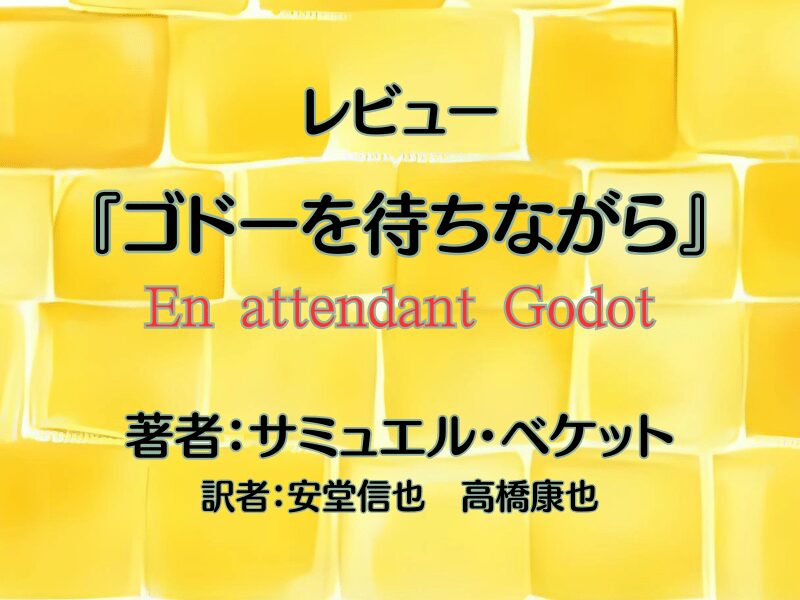
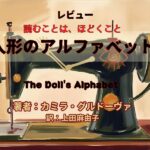
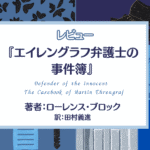
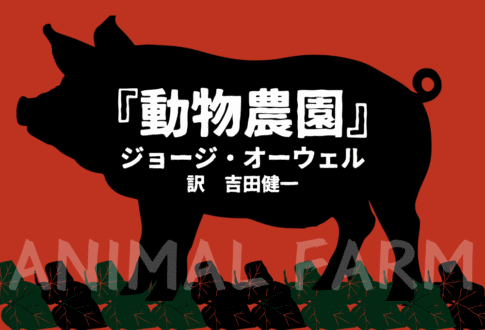
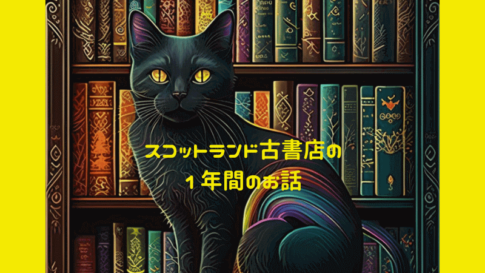
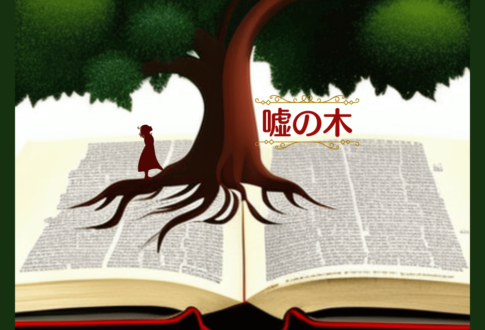

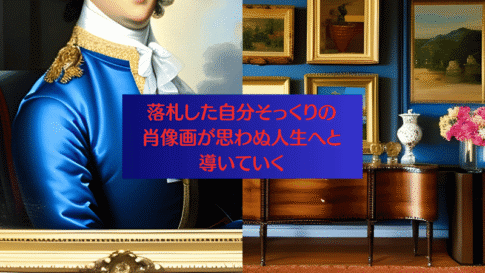




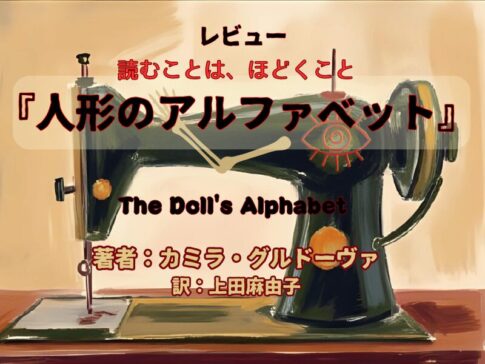
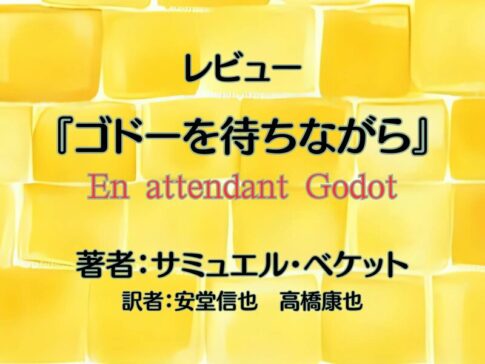
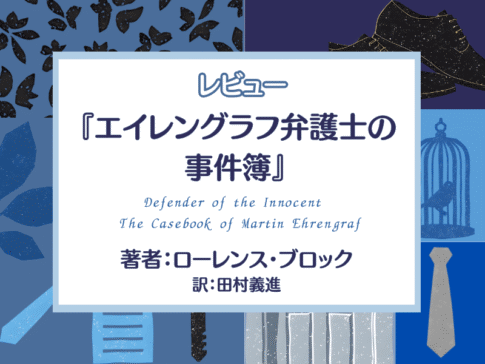
哲学っぽいけれど、意外と笑える。
読むと人生の余白が好きになりそうです!