ステファン・テメルソンの『缶詰サーディーンの謎』(原題The Mystery of the Sardine)を読みました。
舞台はイギリス〜〜マヨルカ島〜〜ポーランド。

タイトルから推理小説を想像しましたが、実際にはもっと奇妙で、不条理で、どこか哲学的な響きをもつ作品でした。
ではさっそく感想を綴っていきたと思います。
タイトル:『缶詰サーディーンの謎』
著者:ステファン・テメルソン
翻訳:大久保 譲
出版社:国書刊行会
出版日:2024年9月15日
Title: The Mystery of the Sardine
Author: Stefan Themerson
Country of Publication: United Kingdom
Year of Publication: 1986
Genre: Absurdist fiction / Experimental novel / Satirical fiction
謎は解かなくていいのかもしれない
物語は「謎」を提示しながらも、解決に向かわないまま進んでいきます。
むしろその解けなさこそがテーマであり、まるで「これは事件なのか?それとも人生そのものなのか?」と読者を翻弄するための仕掛けのようです。
タイトルにある缶詰サーディーンは、物語の中で具体的に描かれるわけではありません。

ですが、読むうちにぎゅうぎゅうに詰め込まれたサーディーンの姿を想像し、それが社会に押し込められて生きる私たち自身の比喩のように感じられます。
こうした解釈の余地があるのも、この小説の面白さなのでしょう。
さらに随所に差し込まれる哲学的な表現や思索的なフレーズが印象的でした。
心に残った箇所の引用
公理は不滅ではない
政治は不滅ではない
詩は不滅ではない
良いマナーは不滅である
ユーモラスで不条理な場面に、ふと深い問いが顔をのぞかせる。その落差がわたしの心に余韻を残しました。
黒いプードル

作中には、黒いプードルが登場します。
何を意味していたのか?と、とても印象に残る登場です。
ミステリのようでミステリではない、謎に振り回される楽しさを味わえる稀有な一冊です。
読後は奇妙な旅を終えたような感覚が残り、なんとも言えずクセになる作品。
謎を解くために読むのではなく、謎に惑わされることを楽しむ。そんな読書体験でした。
『缶詰サーディーンの謎』は1986年に出版された小説
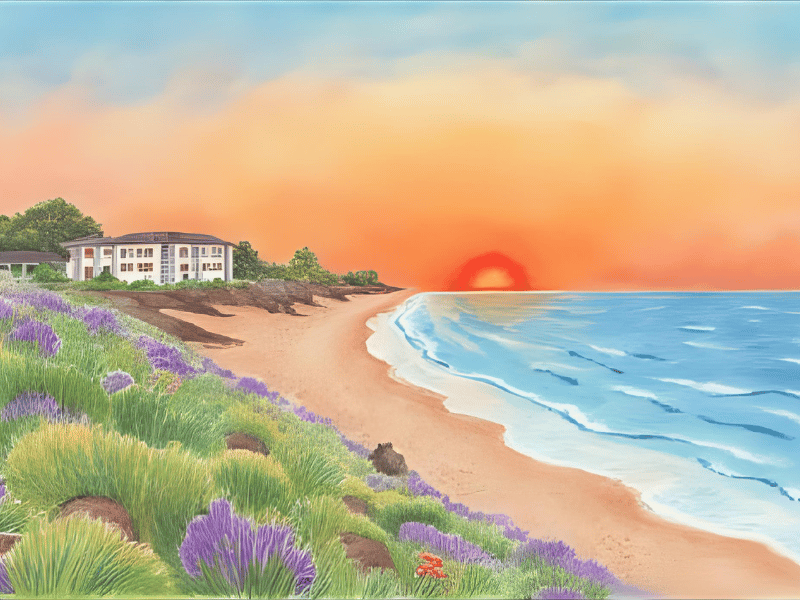
ステファン・テメルソンの『缶詰サーディーンの謎』(原題:The Mystery of the Sardine)は、1986年に出版された小説です。
すでに40年近く前の作品になりますが、読んでみるとまったく色あせず、むしろいまの時代にこそ響くような不思議さを持っていました。
缶詰の中のサーディーンが、型にはめられ、押し込められるように生きる人間の姿。テメルソンは直接語らずに、そうした暗喩を読者に委ねているように感じます。
ステファン・テメルソン 簡単プロフィール
ポーランド出身で、イギリスで活動した前衛的な作家ステファン・テメルソン
ステファン・テメルソン
Stefan Themerson
生没年:1910年〜1988年
出身:ポーランド・プウォツク生まれ。のちにイギリスに移住。
経歴
ワルシャワ大学で物理と建築を学ぶ。
1931年、画家・イラストレーターの フランチシュカ・ウェインレスと結婚。
戦後はイギリスに拠点を置き、二人は出版社ガバーボカス社(Gaberbocchus Press, 1948年創設) を運営。
前衛的・実験的な文学や芸術作品を多く世に送り出す。
文学・作品
ジャンルにとらわれず、不条理・風刺・ユーモアに哲学的な要素を織り交ぜた独自の小説や詩を執筆。
晩年の代表作に、奇妙で実験的な小説 『缶詰サーディーンの謎』(The Mystery of the Sardine, 1986) がある。
晩年
1988年、妻フランチシュカが亡くなった数ヶ月後、ステファンも世を去った。生涯を通じて二人三脚で創作活動を続けた夫婦だった。
まとめ
1980年代の作品でありながら、現代の私たちにも十分通じるテーマを含んでいる点がとても印象的でした。


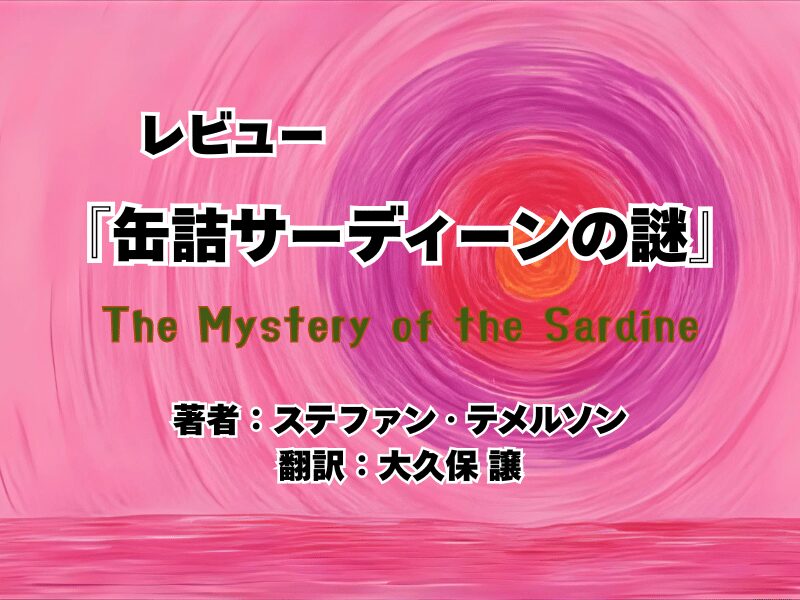
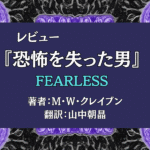


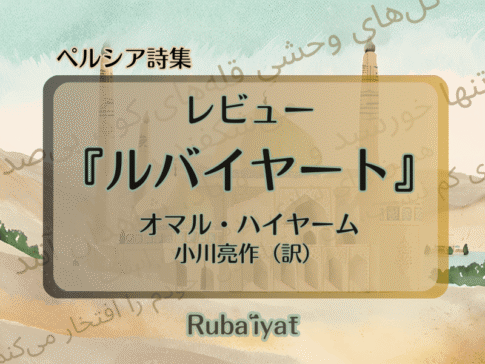
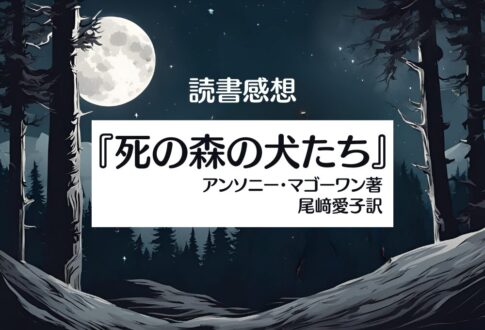

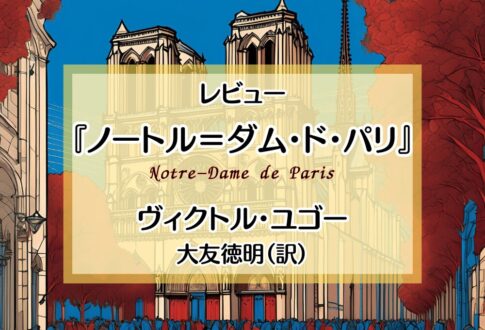

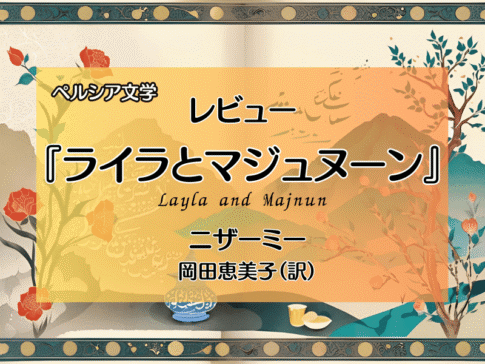
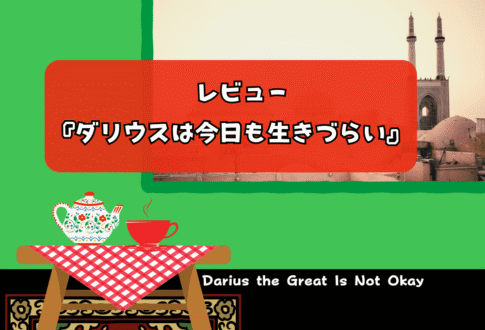

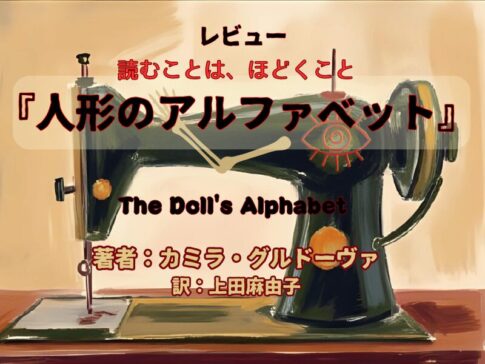
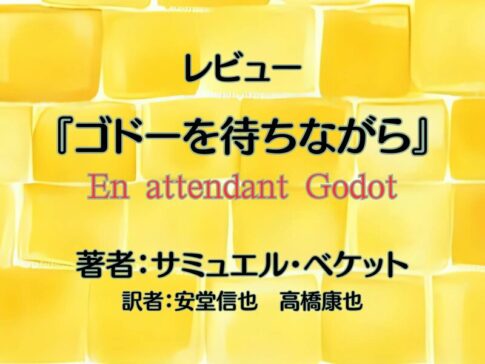
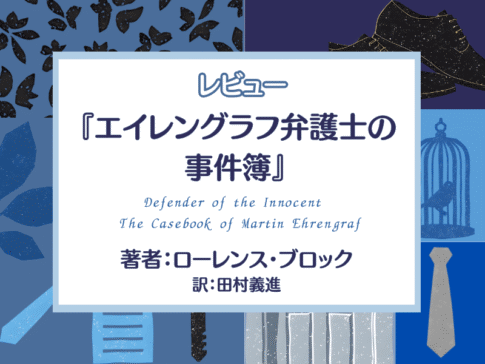
「謎に翻弄される楽しさ」を味わいたいかたにおすすめの一冊です!